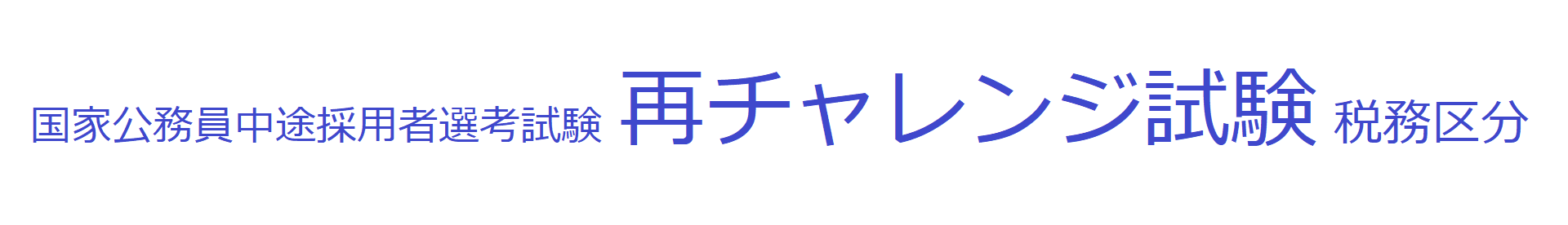教養試験
この試験は45問を100分で解く学力試験です。例年8時55分から10時35分に行われます。詳しい試験内容は問題集が数多く出版されているので参考にしてください。国家Ⅲ種(税務職)の問題集を使用すればよいでしょう。出題範囲は一般知識(政治、経済、社会、日本史、世界史、地理、文学、芸術、国語、数学、物理、化学、生物および地学)、知能(文章理解、英文)、判断推理、数的推理、資料解釈で計45問です。配分の例として、政治2、経済2、倫理または社会1、日本史2、世界史2、地理2、文学または芸術1、国語2、数学1、物理2、化学2、生物1、地学2、文章理解5、古文1、英文3、判断推理8、数的推理4、資料2の計45問を目安と考えてください。この試験
の1次合格の最低ラインは、7割と考えておきましょう。45問中、29問正解で最終合格している人もいますが、やはり32問以上は正解したいものです。最近は景気の低迷の影響で、受験者が増加し、さらに採用者数の減少もあって多少難化しているようです。
点数を伸ばし易いポイントはやはり判断・数的推理といえます。問題を繰り返し解くことで、比較的短時間で点数を伸ばせます。反対に知識分野は範囲が広すぎて、暗記が大変です。したがって判断・数的推理を「数学が苦手だから」と捨てる行為は、その時点で「試合終了」を意味します。
服装は普段着で行きましょう。スーツを着てくる方がいますが、全く無意味です。それどころか、時間との戦いである適性試験では窮屈になり、かえって不利だと思います。
適性試験
120問を15分で解くスピード試験です。計算、照合、図形など問題はいたって簡単ですが練習を積み重ねないとなかなか多く解けるようにはなりません。図形は特に慣れることが必要です。この試験の点数化の仕方は変わっていて、正答数から誤答数を引くことになっています。たとえば89問できても14問まちがっていれば正答数は75ですから、75から誤答数14をひいて61点ということになります。
間違っても「誤答」になりますが、飛ばしても「誤答」となります。したがって苦手な問題を「飛ばす」ことはかなり危険な行為です。この試験にはいわゆる足切り(35%、42点)があるといわれています。また30歳を過ぎると、この手の試験はかなり速度が落ちてしまいます。試験の内容により平均点が大幅に変わります。少しでもよいので毎日練習すればだんだん速くできるようになってきます。
この試験は教養試験のあと、答案回収に引き続き行われます。ということは、かなり長い間トイレに行けないことになります。試験地によっては配慮してくれるところもあるようですが、こちらから要求しない限り行けない場合が多いです。当日朝の飲料の飲みすぎにも注意したほうがよさそうです。
作文試験
試験は1次で行われますが、結果は2次で反映されます。友人についてなど様々なテーマで出題されますが、これからの仕事に結びつくような出題が多いです。
600字で50分以内で書きます。なお字数、制限時間は変わることがあり注意が必要です。ポイントですが誤字、脱字は真っ先に減点要素になります。文字数ですが、やはり字数制限ぎりぎりで書くことが好ましいようです。余りに余白が多かったり(
8割、480字以下)、字数を超えてダラダラ書くのはよくありません。特に6割、360字以下では合格は厳しいと思って下さい。字数を超えて裏面に書くことは認められていますが
、減点の要素となるとも言われているので、できるだけ避けたいものです。内容についてはあまり過激なものや偏重のあるもの、テーマから逸脱したものは嫌われますので
やめてください。
例年11時55分から12時45分の間で行われます。以下は過去3年間の出題目です。
出題目
平成19年 「人とコミュニケーションをとる際に心がけていること」
平成20年 「仕事に責任をもつということ」
平成21年 「少子高齢化について思うこと」
平成22年 「現代の食生活について思うこと」